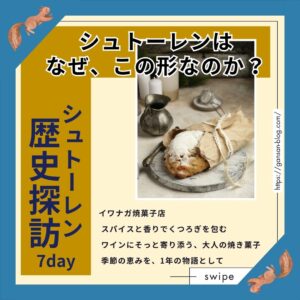商人が運び、兵士が広めた——世界を旅したシュトーレン
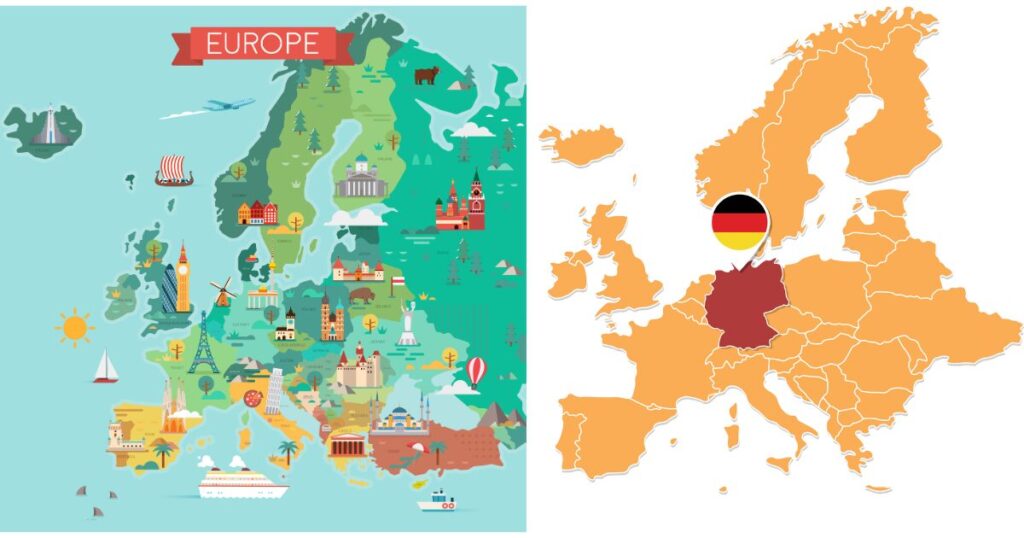
シュトーレンはどうやって世界に広がったのか?
― 商人・移民・戦争が運んだ「クリスマスの味」
私たちにとっては「冬の定番」とも言えるドイツの伝統菓子・シュトーレン。
けれどもこの菓子が、もともとごく限られた地域の、宗教的な意味合いを持つパンだったことを考えると、今日のように世界中で食べられているのは驚きかもしれません。
では、いったいなぜ、どうやってシュトーレンは世界へと広がっていったのでしょうか?
その背景には、「商人」や「移民」——そして、なんと「戦争」までもが関係していたのです。
旅する商人が運んだ、クリスマスの甘い文化
中世ヨーロッパ、各地を旅して商品を売り歩いた商人たちは、物だけでなく文化や風習も運ぶ存在でした。
ドイツの商人たちは、クリスマスの時期になると郷土の特別な菓子であるシュトーレンを携え、フランス、スイス、イタリア、北欧諸国などへと旅を続けました。
その土地で見たことのない菓子——
- ドライフルーツやナッツがぎっしり詰まった甘くて香ばしいパン
- 粉砂糖に覆われたその姿は、まるで雪に包まれた贈り物
こうして、“ドイツのクリスマスの味”は各地で静かに浸透していったのです。
故郷の味を携えて——移民とともに歩んだシュトーレン
19世紀になると、ドイツは戦争・経済的混乱・産業化の波により、多くの人々が新天地を求めて国外へ移住します。
特にアメリカ、カナダ、オーストラリアなどへ渡ったドイツ人たちは、新しい土地に暮らしながらも、自分たちの文化や味を忘れませんでした。
シュトーレンはその象徴のひとつ。
クリスマスが近づくと、家庭ごとに焼き上げる習慣を守り、近隣の人々とも分かち合ったといいます。
そのおいしさと特別感に魅せられた現地の人々も、徐々にこの菓子を受け入れていくように——
シュトーレンは、“移民文化”とともに根付いた世界のクリスマス菓子へと変化していったのです。
そしてもうひとつの要因——「戦争」も、広がりに関与していた
一見すると相反するようにも思える「戦争」と「焼き菓子」。
しかしシュトーレンは、20世紀の2度の世界大戦の中で、さらに広く知られるようになります。
戦地での「故郷の味」
第一次・第二次世界大戦の中で、ドイツ軍が各地に駐留した際、兵士たちが故郷から送られたシュトーレンを食べていたという記録があります。
不安と疲労の中、シュトーレンは彼らにとって**「クリスマスを思い出す、心のよりどころ」**となりました。
戦後、広がった「平和の象徴」としての菓子文化
戦争が終わったあと——
ドイツから持ち帰られた菓子レシピや文化は、各国で少しずつアレンジされながら残り、やがて“平和な暮らし”を象徴する冬の風物詩として、世界中の家庭にシュトーレンの香りが広がっていったのです。
「ドイツの菓子」から「世界のクリスマスの味」へ
こうしてシュトーレンは、交易・移民・戦争という意外な要因を経て、ドイツの伝統を越えた**“世界の菓子”**としての立ち位置を獲得していきました。
今では日本でも、12月になると百貨店やパン屋で目にするようになりましたが、そこには遠い国の人々の、「文化をつなぎ、分かち合いたい」という想いが詰まっているのかもしれません。
次回予告|「ヨーロッパ各国に見る、シュトーレンの広がり」
次回は、ドイツを飛び出したシュトーレンが、フランス・イタリア・北欧などでどんなアレンジをされているのか?
その違いや共通点、そして各国のクリスマス文化との融合についてご紹介します。
シュトーレンのご案内
歴史と文化を感じながら、味わうひととき。
イワナガ焼菓子店では、伝統にインスパイアされた“スパイス香る大人のシュトーレン”をご用意しています。